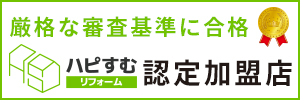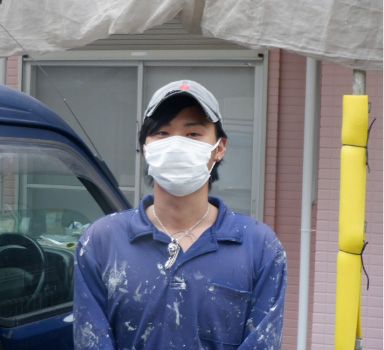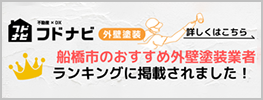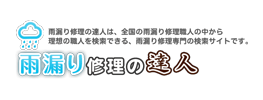ARTICLE
コラム内容
台風被害で火災保険が使えるケースとは?申請前に確認したいこと
2025.06.26

突然の台風被害に遭われ、大切なお住まいの損傷を前にどこに相談すれば良いのか分からないという悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
台風被害の修理に火災保険が使えるという話は聞いたことがあっても、「本当に使えるの?」「手続きが複雑で難しそう」「悪質な業者に騙されたくない」といった不安から、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。
この記事では、多くの住宅修理に携わってきた専門家の視点から、皆様の疑問や不安を解消できるよう、耐風被害の火災保険適用について分かりやすく解説していきます。
火災保険は台風被害の修理に使える?

「火災保険」という名称から、火事の時しか使えない保険と誤解されがちですが、実は違います。
現在の火災保険は、火災だけでなく、台風や大雪などの「自然災害」による損害や、日常生活での突発的な事故による損害まで幅広く補償する「住まいの総合保険」としての性格が強くなっています。
まずはご自宅の保険証券を確認
台風による被害は、火災保険の「風災・雹災(ひょうさい)・雪災」補償などによってカバーされるのが一般的です。
お手元に保険証券をご用意いただき、どの補償が付帯しているかを確認することが第一歩です。どこを見ればよいか分からない場合は、保険証券に記載されている保険代理店や保険会社のカスタマーサービスに問い合わせてみましょう。
台風被害に関わる火災保険の主な補償内容
保険の保証内容で特にチェックしていただきたいのが「風災」の補償が付いているかです。
「風災」とは、台風、竜巻、暴風などの強い風によって生じた損害を補償するものです。具体的には、以下のような被害が対象となります。
☑強風で屋根瓦が飛んだ、ズレた
☑屋根の棟が浮いた、剥がれた
☑飛んできた物が当たって外壁や窓ガラスが破損した
☑雨樋が強風で変形・破損した
☑雹(ひょう)による損害(雹災)や、大雪の重みによる損害(雪災)も、この補償に含まれていることがほとんどです。
雨漏りの補償についての注意点
雨漏りそのものを補償する保険は基本的にありません。火災保険の対象となるのは、「台風の強風によって屋根や外壁が破損し、その破損箇所から雨水が侵入して起きた雨漏り」です。
経年劣化によるコーキングの切れや防水層のひび割れなどが原因の雨漏りは、対象外となるためご注意ください。
【ケース別】火災保険が使える?具体的な判断基準

ここでは、実際にどのような被害が保険適用の対象となり、どのようなケースが対象外となるのかを、より具体的に見ていきましょう。
適用対象となる可能性が高い被害例
以下のような被害は、台風による「風災」と認定され、保険金が支払われる可能性が非常に高いケースです。
屋根の被害
✔瓦のズレ、割れ、落下
✔スレート屋根材のひび割れ、欠け
✔棟板金の浮き、釘の抜け、剥がれ
✔棟瓦の漆喰やモルタルの崩れ
屋根は、住宅の中で最も風雨にさらされる場所であり、台風被害が最も多く発生する箇所です。ご自身で屋根に上るのは大変危険ですので、必ず専門業者に点検を依頼してください。
外壁の被害
✔飛来物による外壁(サイディング・モルタル)の凹みやひび割れ
✔外壁材の剥がれ、落下
✔コーキング部分の断裂
強風で飛ばされてきた看板や木の枝などが当たって損傷するケースです。
雨樋の被害
✔強風による歪み、変形
✔継ぎ手の外れ
✔支持金具の破損による落下
雨樋は、屋根の雨水を集めて排水する重要な役割を担っています。不具合を放置すると外壁の劣化や雨漏りの原因にもなりますので、早期に修理するようにしましょう。
敷地内の付属物の被害
✔カーポート、テラス、バルコニーの屋根パネルの破損
✔テレビアンテナの倒壊
✔ブロック塀やフェンスの倒壊、破損
建物本体だけでなく、これらの付属物も補償の対象となる場合があります。契約内容によって対象範囲が異なるため、保険証券の確認が必要です。
適用対象外となる主なケース
一方で、以下のようなケースでは火災保険の適用は難しくなります。
経年劣化による損傷
火災保険は、あくまで「突発的な事故」による損害を補償するものです。長年の使用による自然な劣化(サビや腐食、コケの発生、塗装の色あせなど)は補償の対象外です。
業者の中には、経年劣化を「台風のせい」として虚偽の申請を勧めてくるケースがありますが、詐欺罪に該当しますので絶対に応じてはいけません。
損害額が「免責金額」を下回る場合
多くの火災保険契約には「免責金額(自己負担額)」が設定されています。例えば、免責金額が20万円の契約で、修理費用が15万円だった場合、損害額が免責金額を下回るため保険金は支払われません。修理費用が30万円だった場合は、30万円から20万円を差し引いた10万円が支払われます。
保険のタイプによっては、定められた金額以上の損害に対しては全額支払われる「フランチャイズ方式」契約もありますので、保険証券に記載されている内容を詳細にご確認ください。
被害発生から3年以上が経過している
保険法により、保険金を請求する権利は損害が発生した時から3年で時効となります。かなり前の台風被害であっても3年以内であれば申請は可能ですが、時間が経つほど「台風による被害」であることの証明が難しくなるため、被害に気付いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
失敗しない!火災保険の申請から工事完了までの7ステップ

ここでは、保険申請から工事完了までの流れを7つのステップで分かりやすく解説します。
STEP1:被害状況の確認と証拠写真の撮影
①まずは落ち着いて、被害箇所を確認します。安全な範囲で「いつ、どこで、何が、どのように」②被害を受けたのかを記録しておきましょう。
③そして最も重要なのが証拠写真の撮影です。以下のポイントで複数枚撮影してください。
④家の全景(どの部分の被害か分かるように)
⑤被害箇所のアップ(損傷具合が分かるように)
⑥様々な角度からの写真
これらの写真は、後の保険会社への状況説明や、申請書類として非常に重要な証拠となります。
STEP2:保険会社または代理店への連絡
次に、保険証券に記載されている保険会社の事故受付窓口や、契約した保険代理店に連絡を入れます。
伝える内容は以下の通りです。
①契約者名、保険証券番号
②被害が発生した日時
③被害場所と状況
この時点で、今後の手続きの流れや必要書類について案内がありますので、しっかりメモを取りましょう。
STEP3:専門業者への相談・現地調査・見積もり依頼
保険会社への連絡と並行して、信頼できる修理業者に連絡し、現地調査と修理見積もりの作成を依頼します。この「修理見積書」が、保険会社に損害額を証明するための重要な書類となります。
経験が豊富な専門業者は、保険申請を前提とした見積書の作成に慣れています。被害状況の写真撮影も併せて行い、保険会社に提出するための資料作成をサポートします。
STEP4:保険会社へ必要書類の提出
保険会社から送られてくる「保険金請求書」に必要事項を記入し、STEP3で業者に作成してもらった「修理見積書」や、ご自身で撮影した「被害写真」などを同封して返送します。
その他、「罹災(りさい)証明書」の提出を求められる場合もあります。これは、お住まいの地域の役所で発行してもらえます。
STEP5:保険会社の損害調査
書類提出後、保険会社が損害状況を確認するために、損害保険鑑定人を派遣して現地調査を行う場合があります。
鑑定人は、提出された書類と実際の被害状況を照らし合わせ、被害の原因が台風によるものか、損害額は適正かなどを中立的な立場で判断します。
業者立ち会いのもとで調査を受けると、被害状況の説明がスムーズに進むため安心です。
STEP6:保険金の確定・支払い
鑑定人の調査報告に基づき、保険会社が審査を行い、支払われる保険金の額が確定します。金額に合意すれば、後日指定口座に保険金が振り込まれます。
STEP7:修理工事の契約と施工
保険金の額が確定したら、正式に修理業者と工事契約を結びます。
保険金が支払われる前に業者と契約を急かしたり、着工を迫ったりする業者には注意が必要です。室内への雨漏りなど急を要する修繕が必要な場合以外は、保険金の額が確定し、工事内容と金額に納得してから契約するようにしましょう。
まとめ|台風被害の修理は信頼できる専門業者への相談から
本記事では、台風被害による住宅修理で火災保険を活用するための知識と注意点について解説しました。
オーネストリフォーム株式会社は、千葉県船橋市・八千代市・習志野市を中心に、これまで数多くの火災保険を活用した住宅修理を手掛けてまいりました。
まずはお気軽に、無料相談・無料お見積りをご利用ください。お客様の不安に寄り添い、大切なお住まいを守るための最適なご提案をさせていただきます。